|
 |
積雲や積乱雲のてっぺんにできる頭巾や菅笠のような形の雲
雲の変化は早く、ふつう数分以内にくずれてしまう
|
 もっと写真を見る(※作成中) もっと写真を見る(※作成中) |
|
 |
 頭巾雲の全体的なお話 頭巾雲の全体的なお話
積雲や積乱雲のてっぺんに、まるで頭巾や菅笠、布をかぶせたような雲が現れることがあり、これを頭巾雲といいます。
頭巾雲はよく似たベール雲(velum)と混同されることがありますが、以下のようなちがいがあります。
 頭巾雲 頭巾雲 |
| 雲のてっぺん近くに現れ、雲の規模は小さい。また変化が早く、ふつう数分のうちに消えてしまう。 |
 ベール雲 ベール雲 |
| 雲のてっぺんだけでなく、側面にも見られ、横に大きく広がって雲の帯のようになる。比較的寿命が長く、数十分単位で残ることも珍しくない。 |
ただし、頭巾雲かベール雲か、判別に迷うようなものがあるのも事実で、また頭巾雲とベール雲が混在するように現れることもあります。
太陽の近くにできた頭巾雲は、ときに彩雲になることがあります。
国際雲図帳1930年版でCasual Varieties(たまに見られるもののうち主なもの)のひとつとして「pileus」が取り上げられています。
1956年版には現在と同じ位置づけ、つまり積雲や積乱雲に現れる付属雲となっています。
日本では古くからかつぎと呼ばれています。
国際雲図帳1930年版のpileusに対し、藤原咲平は被状雲(ひじょううん)の名を、石丸雄吉は幞状または頭巾、被状の名を当てています。また伊藤洋三は1956年版の国際雲図帳をもとにづきん雲という名を当てています。
|
| 日本名 |
|
| 国際名 |
|
| 語 源 |
|
| 別 名 |
 かつぎ(総称) かつぎ(総称)
 被状雲(旧名) 被状雲(旧名)
| 雲頂が突き抜けた状態 |
 襟巻雲 襟巻雲 |
|
十種雲形
との関連
|
| 巻 雲 |
- |
| 巻積雲 |
- |
| 巻層雲 |
- |
| 高積雲 |
- |
| 高層雲 |
- |
| 乱層雲 |
- |
| 層積雲 |
- |
| 層 雲 |
- |
| 積 雲 |
○ |
| 積乱雲 |
○ |
|
|
|
 |
 頭巾雲のできかた 頭巾雲のできかた
頭巾雲は、上空に「湿った空気の層」があり、
そこに積雲などの雲のてっぺんが到達したときに発生します。
積雲は上へ上へと成長するため、
「湿った空気の層」に到達すると、
雲のてっぺんがその「湿った空気の層」を
上に向かって押し上げる形となります。
空気は持ち上げられる(=上昇)と膨らんで冷たくなるため、
空気中に含まれていた水蒸気が小さな水の粒となって現れます。
空気が湿っていると、少し持ち上げられただけで
すぐに水の粒ができはじめ、やがて雲として目に見えるようになります。
このとき雲ができるのは積雲が持ち上げた部分だけなので、
積雲のてっぺんに頭巾をかぶせたような形の雲ができるのです。
積雲がさらに成長すると、雲のてっぺんが
できた頭巾雲を突き抜けていきます。
こうなると、頭巾というよりは襟巻のように見えるため、
襟巻雲と呼ばれることがあります。
国際雲図帳における分類では、襟巻雲も頭巾雲の一型として扱います。
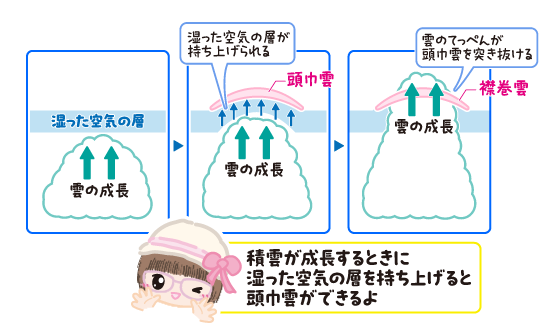
|
 |
 各雲形ごとの説明 各雲形ごとの説明
  積雲の頭巾雲(Cumulus pileus:Cu pil) 積雲の頭巾雲(Cumulus pileus:Cu pil)
積雲のてっぺんに、菅笠や頭巾をかぶせたような、
あるいは布をかぶせたような雲が現れた状態です。
積雲本体に接していることもあれば、
少し離れた位置にできることもあります。
 |
頭巾雲は形の変化が早くてすぐに消えちゃうから、
ベストショットを撮るのがなかなか難しいよ! |
|

  積乱雲の頭巾雲(Cumulonimbus pileus:Cb pil) 積乱雲の頭巾雲(Cumulonimbus pileus:Cb pil)
積乱雲の雲のてっぺんにも、積雲と同様の頭巾雲ができることがあります。
ただ、積乱雲の場合、すでに雲のてっぺんが頭打ちになっていることが多く、
積雲に比べると頭巾雲はできにくいかもしれません。
|

